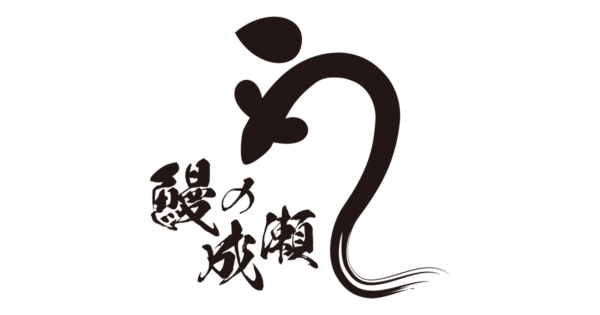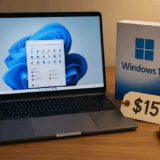「うな重が1600円」と聞いて、驚いた方も多いのではないでしょうか。
高級食材として知られるうなぎをリーズナブルな価格で提供している鰻の成瀬は、今や全国に200店舗以上を展開する注目のチェーンです。ですが、ここまで安いとなると、「どこ産の鰻を使っているのか」「中国産なのになぜ安心なのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。
本当に安全なのか、安さの裏にあるビジネスのカラクリとは何なのか。
この記事では、鰻の成瀬 安い理由にまつわる数々の疑問に、丁寧にお答えしていきます。飲食経験のない経営者が立ち上げたにもかかわらず、急拡大している背景には、綿密に計算された仕組みが隠されています。
価格だけでなく、品質や安全面についても不安なく知っていただけるよう、わかりやすく解説していきます。
この記事を読むとわかること
- 鰻の成瀬 安い理由の具体的な仕組み
- 鰻の産地がどこ産で、なぜ中国産でも品質が保たれるのか
- 安くても安全性が確保されている根拠
- メニューや流通、調理体制などのカラクリ
鰻の成瀬が安い理由を徹底的に解説
- 価格が安いカラクリはどこにあるのか
- 中国産なのになぜ品質が保たれるのか
- どこ産のうなぎか具体的に知りたい人へ
- セントラルキッチンと焼き機の仕組み
- 流通経路の工夫でコスト削減に成功
- メニュー構成のシンプル化が価格に影響
価格が安いカラクリはどこにあるのか
「鰻の成瀬」の価格の安さには、明確な仕組みがあります。飲食業界において鰻は一般的に高級食材とされ、特に近年は仕入れ価格の高騰が続いている中で、「うな重」が1600円から食べられるというのは多くの人にとって驚きです。ですが、この安さは単なる偶然や企業努力だけで実現されたものではありません。そこには、明確な「カラクリ」があります。
まず注目すべきは、鰻を専門とした職人に頼らない運営体制です。従来の鰻専門店では、職人による手焼きや丁寧な仕込みが行われ、その分人件費が高くなる傾向にあります。しかし鰻の成瀬では、独自開発された焼き機を導入することで、調理工程を大幅に簡素化しています。これにより、アルバイトスタッフでも扱えるようなオペレーションが可能となり、高度な職人技を必要とせずに安定した品質の鰻を提供できるようになっているのです。
次に、店舗戦略にもコストを抑える工夫が見られます。鰻の成瀬は一等地を避け、あえて「二等立地」や「三等立地」と呼ばれる場所に出店しています。駅から少し離れた住宅街など、人通りがそこまで多くない地域でも「目的来店型」の飲食である鰻ならば、集客が見込めるという判断です。その結果、初期費用や家賃を大幅に抑えることができ、価格に反映されているわけです。
また、居抜き物件を活用している点も見逃せません。既存の飲食店設備をそのまま再利用することで、内装費用や設備投資を大幅に削減しています。加えて営業時間も短縮されており、スタッフの雇用コストも抑えやすい構造になっています。
こうした全体のオペレーションは、すべて「価格を下げるため」に設計されており、裏を返せば無駄な部分を徹底的に省いたビジネスモデルとも言えます。つまり鰻の成瀬の安さは、品質を犠牲にせずに実現された戦略的な構造に基づいたものだと理解できます。
中国産なのになぜ品質が保たれるのか
「中国産うなぎ」と聞くと、なんとなく不安を感じる方は少なくないでしょう。しかし、鰻の成瀬ではその不安を払拭するために、品質管理において極めて高い基準を設けています。安価でありながら一定以上の品質を保てる理由は、選び抜かれた供給体制と管理体制にあります。
まず、鰻の成瀬が使用しているのは「ニホンウナギ」です。これは国産うなぎと同じ種類であり、品種そのものに差はありません。養殖の場所が中国であるという点が主な違いです。つまり、「中国産=低品質」という先入観は必ずしも正しくなく、鰻の成瀬が選定している鰻は、しっかりと管理された環境下で育てられたものになります。
さらに、鰻の成瀬では、中国の養殖場に対して厳しい品質基準を設けています。ISO9001、ISO22000、HACCPといった国際的な食品安全管理の認証をクリアしている施設のみと契約し、安全な加工・輸出体制を確保しています。これにより、日本国内に輸入される段階で一定の安全性が担保されているのです。
加えて、鰻は現地で一次加工(さばき・焼き)され、日本国内では焼き直しをするだけの状態で届きます。この加工プロセスも一定の基準を満たしており、味や品質に影響を与えないような冷凍技術が用いられています。つまり、工程が短縮されている分、味の安定化にも繋がっているのです。
もちろん、こうした管理が行き届いていても、店舗での扱いによっては味に差が出ることもあります。ただし、その点についても、後述する焼き機の技術によって極力バラつきを抑える仕組みが採用されています。
このように、「中国産=不安」という図式は、鰻の成瀬においては当てはまりません。むしろ、適正なコストと安全性のバランスを取ることで、高いコストパフォーマンスを実現している事例といえるでしょう。
どこ産のうなぎか具体的に知りたい人へ
「鰻の成瀬」で提供されている鰻がどこ産かについては、公式サイトや関連資料でも明記されています。それによると、主に中国の養殖場で育てられた「ニホンウナギ」が使用されています。この情報だけを聞くと、「外国産なのか」と少し不安を感じる方もいるかもしれませんが、実際には安心できる根拠が多数存在します。
中国産とはいえ、育てられているのは日本でも昔から親しまれている「ニホンウナギ」です。生物種としては同じため、正しく育成されれば味や栄養価に大きな違いはありません。むしろ、鰻の成瀬が契約している養殖場では、日本の鰻専門企業とも連携し、独自の餌や水質管理によって、より風味の良い鰻を育てる努力がされています。
ここで注目すべきは、「水」に対するこだわりです。育成環境で最も品質に影響するのが水質であり、ここに清浄で管理された水が使用されていることで、くさみのない、脂の乗った鰻が育ちやすくなります。また、仕入れルート自体も、過去に山本社長が携わっていたうなぎ専門企業との協力関係によって、安定した品質を確保しています。
店舗に届くまでのプロセスも、一次加工済みの状態で冷凍され、日本国内の衛生基準を満たしたルートで配送されています。このため、国産品と比べて衛生面で劣るということはありません。
そして、こうした産地や養殖環境の透明性が確保されていることで、店舗スタッフが客からの質問に正確に答えられるようになっており、安心して食べられるような取り組みも行われています。
産地について詳しく知っておきたいと考える方にとって、「中国産=不安」という思い込みを解消できる情報は、実はすでに提供されているのです。
セントラルキッチンと焼き機の仕組み
「鰻の成瀬」が全国展開できた背景には、調理工程の一元化があります。特にセントラルキッチンと独自の焼き機の導入は、オペレーションの合理化と価格の低下に大きく寄与しています。
まず、セントラルキッチンの役割ですが、ここでは鰻の一次加工(さばき・焼き)を事前に行い、それを冷凍した状態で各店舗に配送しています。この方式により、各店舗での調理時間は大幅に短縮され、仕込みや焼き工程の技術的なブレが抑えられます。
続いて、店舗では再加熱と焼き直しを行うのみとなります。この工程を担うのが「独自開発の焼き機」です。この機械はボタン一つで蒸しと焼きを自動で行い、職人のような手間をかけることなく、ふっくらした鰻を仕上げることができます。
この仕組みの最大のメリットは、調理の均質化とスピード化です。たとえば、経験の浅いアルバイトスタッフでも数分でうな重を提供できるため、人件費が抑えられるだけでなく、提供時間も平均5〜8分という速さを実現しています。
また、焼き機には煙を出さない仕様が組み込まれており、通常であれば「重飲食」に分類される鰻屋も、物件によっては「軽飲食」として営業できることがあります。この点は出店の自由度を上げ、カフェなどの居抜き物件も活用しやすくしているのです。
鰻の成瀬がこのような革新的な仕組みを導入しているからこそ、低価格かつ大量出店が可能となっているわけです。
流通経路の工夫でコスト削減に成功
鰻の成瀬が実現している「低価格かつ安定供給」は、流通経路における独自の工夫によって支えられています。通常、高級食材であるうなぎは、産地から出荷されてから消費者の口に入るまでに、いくつもの中間業者を介します。そのたびに手数料や保管費用、輸送費用などが加算され、最終的な価格に跳ね返ってしまいます。
この点において、鰻の成瀬は大きく異なります。同チェーンでは、養殖場から店舗までの流通経路を極限までシンプルにしています。まず、中国などの海外の養殖場で飼育・加工されたうなぎは、冷凍処理された後に直輸入されます。一般的なうなぎ業界のように複数の卸業者を介するのではなく、提携企業との専用ルートを構築しているため、中間マージンを最小限に抑えることが可能です。
さらに、輸入された鰻は一度セントラルキッチンでチェック・管理され、各店舗に直接配送されます。この過程においても、余計な在庫や再加工を行わないことにより、物流コストを低減できているのです。
H4 店舗ごとの在庫リスクを最小化
もう一つ重要なのは、各店舗が在庫を抱えにくい仕組みを採っている点です。一括仕入れによるスケールメリットを活かしつつ、必要量のみが店舗に届けられるため、無駄な仕入れロスや在庫腐敗のリスクを避けられます。
この仕組みにより、物流の無駄を徹底的に排除し、価格の安定と提供スピードの両立が実現されています。ここまで流通に合理化を取り入れている鰻チェーンは極めて珍しく、まさに「安さの裏にある工夫の結晶」といえるでしょう。
また、物流の簡素化は、今後の海外展開や地方へのさらなる出店にも柔軟に対応できる基盤となっており、成長性の観点からも大きな強みです。
メニュー構成のシンプル化が価格に影響
鰻の成瀬の特徴の一つに、「徹底的に絞り込まれたメニュー構成」があります。この戦略も、価格に大きな影響を与えている重要な要素の一つです。多くの飲食店では、来店者の選択肢を増やすために多彩なメニューを用意する傾向がありますが、それに伴い仕入れ品目は増え、調理工程も複雑になります。当然ながら、コストや人員、在庫管理の負担が大きくなるため、それが価格にも反映されてしまいます。
一方で、鰻の成瀬では、うな重は「松・竹・梅」の3種類のみ。違いは鰻の量と価格だけで、味付けやタレ、ご飯、付け合わせはすべて共通です。この明快な構成によって、店舗側のオペレーションは極めてシンプルになります。
調理工程も簡略化されており、調理スタッフはオーダーに応じて鰻を焼き機にセットするだけで済みます。また、仕入れ食材の種類が少ないことで、在庫管理の手間やロスも大幅に削減されています。このように、メニュー数が少ないことは、単なるシンプルさ以上に、コスト削減に直結する構造を持っているのです。
ゴルディロックス効果の活用
また、価格帯の設定に関しても、「ゴルディロックス効果」をうまく活用しています。松竹梅の3つの選択肢を提示することで、多くの人が中間価格の「竹(2200円)」を選ぶ傾向があります。これは「一番高くもなく安くもない、ちょうどいい選択」として心理的に選ばれやすい価格帯だからです。
このような行動心理学に基づくメニュー戦略により、店舗側は一定の客単価を維持しつつ、提供オペレーションの効率化を実現しています。多くの飲食店が「メニューは多いほど良い」と考える中で、鰻の成瀬はあえて逆を突く形で、価格競争力を獲得しているのです。
結果として、このシンプルなメニュー構成は、厨房の省力化、人員配置の最適化、原価管理の容易化など、店舗運営のあらゆる面でメリットを生み出しており、それが消費者に対する「低価格」という形で還元されているといえるでしょう。
鰻の成瀬 安い理由と安全性の関係とは

- 安くても安全な理由と品質管理体制
- HACCP・ISO取得による安全への配慮
- 店舗ごとの味や品質のばらつきについて
- 他チェーン店との違いを比較してみた
- 子どもにも安心?家庭向けに適した理由
- 運営会社とフランチャイズ本部の信頼性
安くても安全な理由と品質管理体制
「鰻の成瀬」が提供するうな重は、価格の安さに注目が集まりがちですが、実際には安全性にも十分な配慮がなされています。安い=危険という印象を持つ方もいるかもしれませんが、このチェーンが構築している品質管理体制を見ると、その不安は杞憂であることが分かります。
まず、安全性の根本を支えているのが、鰻の供給元に対する厳格な基準です。鰻の成瀬が使用している鰻は主に中国の養殖場で育てられたものですが、そこでは国際的な衛生基準に基づいた環境管理が徹底されています。育成に使用される水は清潔で、独自配合のエサを用いることで、くさみのない良質な鰻に仕上がるよう工夫されています。
このようにして育てられた鰻は、現地で一次加工され、冷凍状態で日本へと輸送されます。輸送後はセントラルキッチンや各店舗で解凍・加熱の工程を経て提供されますが、この工程でも安全性が担保される仕組みが整っています。
また、全体のオペレーションがマニュアル化されていることも、安全性維持に大きく貢献しています。例えば、焼きの工程は誰が操作しても品質を保てるように設計された焼き機によって行われるため、調理ミスや焼きムラによる衛生リスクを最小限に抑えることが可能です。
さらに、店舗では必要最小限の食材しか扱わない構造となっているため、在庫の劣化や腐敗といったリスクも低く抑えられています。こうした設計は、食中毒リスクのある夏場にも安定して営業できる背景となっています。
安価な商品であっても、適切な管理体制とオペレーションによって、高い安全性を維持できる。鰻の成瀬の事例は、その良い見本と言えるでしょう。
HACCP・ISO取得による安全への配慮
食品の安全管理において、近年ますます重要視されているのが「HACCP」や「ISO」の取得です。鰻の成瀬では、これらの国際基準を満たす仕組みを取り入れることで、鰻という高リスク食材を扱いながらも安心して提供できる体制を築いています。
まずHACCPとは、食品の製造・加工過程におけるリスクをあらかじめ分析し、重要な管理点を常に監視・記録するという仕組みです。これにより、従来の抜き取り検査に頼るのではなく、全工程での安全性を担保することができます。鰻の成瀬が契約する海外の加工場では、このHACCPの考え方に基づいた管理が徹底されており、現地での衛生状態が常に監視されています。
加えて、ISO9001やISO22000といった品質・食品安全管理に関する国際認証も取得済みの供給先と提携しているため、衛生面だけでなく業務プロセス全体において信頼性が高いのが特徴です。
見えない管理を「見える化」する努力
これらの安全管理体制は、消費者にはなかなか目に見えにくい部分ですが、鰻の成瀬では「こだわりシート」などを活用して店舗内でも情報提供を行っています。こうした取り組みにより、消費者は食材の背景や安全管理について理解を深めることができ、不安を感じずに食事を楽しめるよう配慮されているのです。
価格だけでなく、安全性についても高い基準をクリアしていることから、鰻の成瀬は「安かろう悪かろう」という一般的なイメージを覆す存在だと言えるでしょう。
店舗ごとの味や品質のばらつきについて
フランチャイズ展開をしている飲食チェーンにおいて、避けては通れない課題の一つが「店舗ごとの品質のばらつき」です。鰻の成瀬も例外ではなく、ネット上の口コミやレビューでは、味の濃淡やご飯の炊き加減などに違いがあるという意見が散見されます。
このばらつきが生じる主な要因は、スタッフの経験値や店舗ごとのオペレーション対応にあります。店舗での作業は簡略化されているものの、米の炊き方やタレのかけ具合など、細かい作業にはどうしても人の手が加わるため、その部分で差が出るのです。
また、本部のスーパーバイザーによる定期巡回や指導が少ないこともばらつきの原因の一つとされています。軽量なオペレーションを維持するため、本部の関与を最小限にしていることが、逆に品質の一定化を難しくしているとも言えるでしょう。
一方で、焼きの工程に関しては、独自の機械によって「誰でも一定の仕上がりを実現できる」よう設計されており、最も重要な鰻の加熱には大きな差が出にくくなっています。つまり、全体としての味の構成は守られており、大きな失敗が起きにくい構造にはなっているということです。
今後さらなる店舗数の拡大を目指すのであれば、品質統一の仕組みを強化していくことが求められるのは間違いありません。
他チェーン店との違いを比較してみた
鰻の成瀬を他のうなぎチェーンと比較すると、その特徴がより明確になります。代表的な比較対象としては、「すき家」などの大手牛丼チェーンで提供されるうな丼や、「うな匠」のような専門店系フランチャイズが挙げられます。
まず価格面では、鰻の成瀬が中間価格帯に位置しているのが特徴です。すき家などのチェーン店は500円〜1000円台のワンコインメニューが中心で、コスト重視のユーザー層に人気があります。一方、「うな匠」などは一食で3000円〜5000円程度とやや高級路線です。
この中で鰻の成瀬は、1600円〜2600円の価格帯で、量・品質・価格のバランスを追求しています。まさに、従来不在だった「中価格帯市場」を狙った立ち位置です。
味の方向性としては、すき家のうなぎはやや甘めのタレで、ご飯との相性重視の構成ですが、成瀬のタレは比較的あっさりとした甘辛で、大人にも受け入れられやすい印象です。
また、調理工程でも大きな違いがあります。すき家は大量調理・工場出荷型に近く、提供までのスピード重視。一方、成瀬では焼き機による「店舗調理感」を保っているため、チェーンでありながらも専門店に近い印象を与えるのが特徴です。
つまり、成瀬は「価格とクオリティのバランスを求める層」に刺さる戦略を取っているというわけです。
子どもにも安心?家庭向けに適した理由
鰻の成瀬が幅広い世代に支持されている背景には、「家族連れでも安心して利用できる環境」があります。特に子どもがいる家庭にとっては、安全性や味、店舗の雰囲気などが重要なポイントとなります。
まず、味付けに関しては、鰻の成瀬のタレは濃すぎず、甘すぎないため、子どもでも食べやすい味に仕上がっています。実際、来店客の口コミには「子どもが完食した」といった声も多く見られます。
また、量の選択肢があるという点も魅力です。梅(半尾)・竹(3/4尾)・松(1尾)という3段階のメニューは、食欲や年齢に応じて選びやすく、少食な子どもでも無理なく楽しめます。
安全面でも、すでにご紹介したHACCP対応や衛生管理の厳格さがあるため、安心して提供できる品質となっています。もちろん、骨が気になるという声もあるかもしれませんが、加工時に小骨の処理もある程度なされており、極端に食べにくいということはほぼありません。
価格帯も外食としては良心的で、家族4人で訪れても1万円を超えないケースがほとんどです。これは高級店では実現しにくいコスパであり、「気軽な外食」として定着しやすい理由となっています。
運営会社とフランチャイズ本部の信頼性
鰻の成瀬を運営するのは、「フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社」という企業です。この社名からも分かる通り、同社の本業は飲食業ではなく、フランチャイズモデルの設計と展開にあります。
社長の山本昌弘氏は、清掃業界のフランチャイズ本部で約10年間勤務し、加盟店開発や法務まで幅広く経験してきました。その知見を活かして立ち上げたのが鰻の成瀬です。この経歴からもわかるように、「鰻を売りたい」ではなく「勝率の高いビジネスを作りたい」という意図が根底にあります。
本部の運営スタンスは、加盟店の自主性を尊重する形となっており、あえて募集を公にはせず、問い合わせが来た企業にだけ対応するという「引きの営業」を徹底しています。これにより、本当に経営意欲のある加盟者との関係性を築いているのです。
また、加盟店との間で「他責加盟店」を生まないようにしており、「自分で選んで加盟した」という意識があるため、責任ある運営がなされやすくなっています。フランチャイズとしては異例ともいえる強固な信頼関係が、その拡大の原動力にもなっているわけです。
このような運営体制を見る限り、鰻の成瀬は単なる飲食チェーンというより、フランチャイズビジネスの成功事例としても注目される存在であるといえるでしょう。
鰻の成瀬 安い理由をわかりやすくまとめてみました
ここでは、「鰻の成瀬」がなぜリーズナブルな価格でうな重を提供できているのか、その仕組みや背景を総合的にまとめてみました。高級食材であるうなぎを扱いながらも、1600円から楽しめる理由には、きちんとした根拠があります。以下のようなポイントが、価格の安さとサービスの質を両立させている要因となっています。
- 職人に頼らず、独自開発の焼き機で調理の均一化を実現している
- アルバイトでも扱える簡易なオペレーションを導入している
- 焼き機が無煙仕様のため、出店物件の選択肢が広くなっている
- 高額な一等立地ではなく、二等・三等立地に戦略的に出店している
- 居抜き物件を活用することで、内装や設備の初期コストを大幅に削減している
- セントラルキッチンで一次加工を済ませ、店舗では焼き直すだけにしている
- 営業時間を短縮し、人件費を抑えた効率的なシフト体制をとっている
- 「松・竹・梅」の3種のみというメニュー構成で、仕入れと調理の無駄をカットしている
- メニューの価格設定に「ゴルディロックス効果」を活かし、自然に客単価を調整している
- 鰻は中国産だが、使用しているのは日本と同じ「ニホンウナギ」で品質が高い
- 契約する中国の養殖場は、HACCP・ISOなどの国際認証を取得しており安全性が高い
- 流通経路をシンプルにし、中間業者を極力排除してコストを削っている
- 在庫リスクを最小限にする配送体制で、廃棄ロスを大きく減らしている
- 提携先の冷凍・輸送技術により、加工済みでもふっくらした鰻を提供できている
- 運営会社はフランチャイズ支援に特化した企業で、安定した経営体制が整っている
このように、鰻の成瀬の安さには、単なる企業努力ではない「仕組み」が数多く存在しています。うなぎという高級食材をもっと日常的に楽しんでもらうために、徹底した効率化と工夫が積み重ねられているのです。価格に見合わない価値を感じる理由が、ここにあると言えるでしょう。
参考サイト